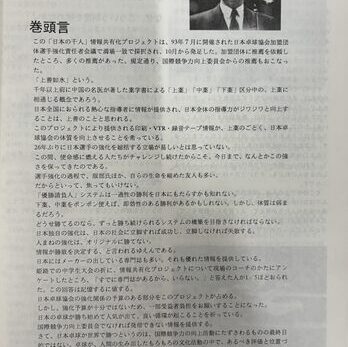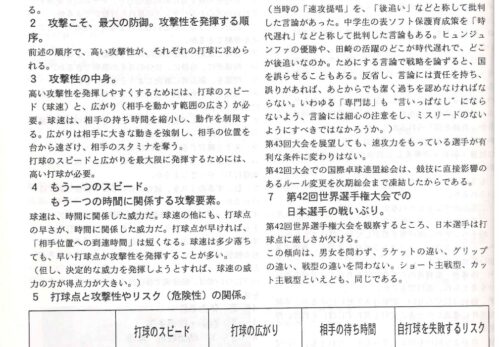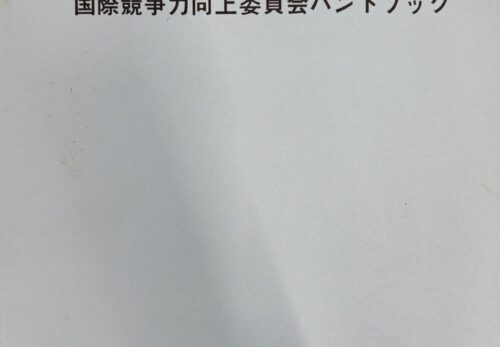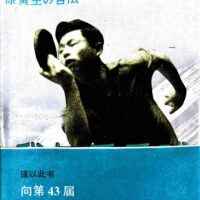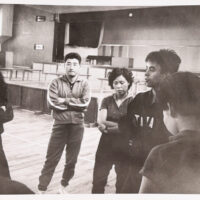学生スポーツ外史・卓球
/荻村伊智朗(国際卓球連盟会長)
「モンタギュー伯爵様 ご招待状 次の日曜日の午後、ピンポンをいたしませんか。そのあと、ダージリンの新茶をご用意いたしております」
二十世紀の初めごろ、英国の上流階級の流行は、お茶会の招待状に「ピンポンの会」と書くことだった。いまも、無数の招待状が残されている。モンタギュー家の息子アイボアがもの心ついたころからの四半世紀、欧米は卓球ブームだった。
新世界アメリカ合衆国で、綿の長繊維を原料とするセルロイド球が発明された。コルクやゴムの塊を毛糸でくるんだボールを打ち合うゴシマは、あっという間に、セルロイドのピンポンにとって替わられた。たおやかなご婦人方には、柄の長い、羊皮を両側に張った軽いラケットで、音色も明るいラリーのピンポンがぴったりだった。
同じころ、ピンポンの流行に感心していた日本人がいた。明治35年、体育取り調べ係として英国に6カ月派遣された、体育学専攻の坪井玄道だった。文明開化を急ぎ、欧米列強の日本進出にいかなる口実も与えまいとした明治新政府は、有為の青年たちを海外に派遣し、海外文化の吸収に努めていた。音楽取り調べ係として渡米した神津専三郎は、帰国して12音階の音楽を教える学校を開いた。嘉納治五郎はスポーツを移植し、学校体育の場を活用して婦女子にも参加の機会を与えていた。
坪井がハタとひざを打った理由の一つには、ピンポンは、老若男女を問わず普及できる、欧米エスタブリッシュメントの流行スポーツだったこともある。
帰国を前に、坪井は英国で一番有名なジェイクス社の卓球台・ラケット・ボールなどを3組求めた。帰路は船であった。インド洋を越え、長旅の末に横浜へ着いた坪井は、旅の疲れをいやすと、卓球台の試作にとりかかった。本郷は赤門の前、美満津運動具店が、坪井の指導のもとに、10台の試作に成功した。坪井は早速、自身が教鞭を執る東京女子高等師範学校・東京高等師範学校などで卓球を広め始めた。
卓球はこうして旧制高校、帝国大学、そして私学に広まり、やがて社会人クラブや官公庁、そして企業内スポーツへと波及してゆく。
坪井があとにした英国では、ピンポンは遊戯から競技へ発展する。母のお供のお茶会でピンポン大好き少年になったアイボア・モンタギューは、ケンブリッジ大学生となり、大学卓球クラブのリーダーを務める。やがてモスクワ留学から帰った彼は、大学院学生のまま、1926年、ロンドンで9カ国の国際会議を招集し、弱冠26歳で国際卓球連盟を創設、初代会長に任ぜられる。以来在任41年、今日の卓球の“平和志向スポーツ”としての名声の基礎を築いた。
大正期に入ると、卓球用具メーカー3社の支配による3つの日本卓球協会が設立され、実学を巻き込んで対立し、ついには神宮大会参加を差し止められる事態を招く。
“家貧しくして孝子出ず”というが、大同団結がなった昭和10年ごろ、学生卓球界に偉才が現れる。天才にして努力家の早稲田の今孝、剣道から転向して学生チャンピオンになった関西学院の渡辺重伍、後に川崎製鉄の社長となり、日本卓球協会の会長を務めて第41回千葉世界選手権大会を成功させた東大の岩村英郎らである。
岩村らの学生卓球連盟幹部たちは、「目を世界に転じよ! 」と大人たちの世界に警鐘を鳴らし、学生卓球ルールを国際式に変更する。これによって、日本の卓球選手の世界選手権大
会出場は、名実ともに可能になってゆくのだから、岩村たちの先見性はみごとであった。
2年後の昭和13年(1938年)、ハンガリーの世界チャンピオンたち、サバドスとケレンの日本遠征が実現する。1月の寒い日、満場立錐の余地もない日比谷公会堂の舞台で、学生チームは思わぬ緒戦完敗に顔色を失う。見たこともなかったラバーラケット、シェイクハンドグリップ、そして消える魔球のフィンガースピンサービス。トップを承った立教大学の川村澄は、ケレンの最初の5本のサービス全部にノータッチの屈辱、そして惨敗。後にアジア大会監督として荻村・富田の世界制覇コンビを薫陶した川村は、舞台の袖で男泣きする。だが、後に球聖とうたわれる今孝が、第2戦からみごとな勝利を収める。そして、渡辺がこれに続く。
日本は勝った。しかし、欧州卓球の技術には目をみはるものがあった。渡辺は伝統のペングリップを捨て、日本のシェイクハンドグリッププレーヤー第1号となる。多感熱血の学
生卓球が日本をリードするかに見えたころ、太平洋戦争による中断が卓球界を襲う。
1950年、「藤井選手の替え玉受験事件」が卓球界を震撼させる。日本選手権を4連覇中の天才藤井則和は、戦後の病苦に倒れた今孝の悲願“世界制覇”を実現できる最大のホープだった。初の全米遠往の直前、関学の卒業試験でのエースの不祥事で、遠征は中止され、岩村らが描いた“学生選手の世界制覇”は、見果てぬ夢に終わるかに見えた。
しかし1953年暮れ、日本卓球界は賭けに出る。
翌54年4月、卓球発祥の地、英国の首都ロンドンで行われる第21回世界選手権大会に、全員が無名の学生新人チームを日本代表として派遣することを決定したのだ。
紛糾した理事会で、豪気をもって鳴る名古屋の後藤理事は、反対派に対して言い放った。「確かに日本卓球協会には金はない。だから、選手に集めさせればいいじゃないか」。
かくして当時1人80万円、90年代の貨幣価値で1200万円の大金を、選手たちがそれぞれ冬空の街頭10円募金やカンパで調達することになり、辛苦の末、遠征が実現した。
「一生に一度の出来事だ。一年留年して、完全な準備をしよう」と、日本大学2年の荻村、専修大学2年の富田、3年の川井、大阪薬科大学の江口らが決議した。岩手大学の優等生の藤井基男は、「君は欧州型の練習相手としてどうしても欠かせない。君も留年しろ」と呼びかけられたが、彼は夜行列車で学年試験中を盛岡・東京間の往復を重ね、そのかいあって、留年はしなかった。
後藤は、学生選手たちの必死の錬磨と、世界を制する満々たる覇気を知っていた。そのくせに、出発を前にして新聞記者たちにこう言った。「この連中は、ロンションだよ。えっ? ロンドンへ行って、小便して帰ってくるだけさ」。満座の中での辱めを受けた若者たちは怒りを堪え切れず、「後藤を見返してやる! 」と誓い合った。
後藤団長の背水の陣は成功した。心理的に千仭の谷に突き落とされた学生たちは自力ではい上がった。劣悪な対日感情が満場の観客を支配し、日本への嫌がらせも相次ぐ中で、平均年齢20歳のチームは大健闘し、荻村の男子シングルスをはじめ、男子団体・女子団体の3種目に優勝した。春まだ浅いウェンブレーの氷雨の中、戦後初の日本人スポーツマンの英国遠征は大成功に終わり、敗戦にうちひしがれていた日本人の気持ちを明るくしたのだった。選手たちは満場割れんばかりの拍手のうちで、モンタギュー会長から金メダルを、母君のスエズリング夫人から優勝杯を授与された。
猛烈な練習量を伝統とする学生卓球界は、その後も英才を送り続け、50年代から60年代にかけて、日本の卓球は世界に君臨し、技術情報の発信地となり、世界の卓球の発展に貢献した。
しかし、学園紛争が、猛練習の伝統を破壊した。日曜祭日の練習場は閉鎖され、ガードマンが深夜練習を謝絶した。学生選手たちは最初の数年間、ジプシー行脚をして練習量の確保に努めたが、やがて少ない練習量になれていった。暁を卓球台の上で迎える練習熱心さは、学生卓球界ではいまや神話の世界。それとともに“勝てない日本”の時代が続いている。しかし、90年代に入って、10年前からスタートした早期教育の成果が出始めている。
一方で、日本の学生卓球連盟が中心となり、世界の学生卓球界の交流が推進されている。コロンビア、UCLA 、MIT、エール、オックスフォード、アルト・ハイデルベルグなど、欧米の大学との交流が、日本学生チームの遠征、相乎校キャンパスでの対抗戦という形で盛んになってきている。
また一方では、かつての感激の遠征を共にした大学OB 選手が中心になり、1000名ほどの同志を世界に募り、貧困・政治的迫害・病気などに悩む昔の好敵手を支援する国際スエズリング・クラブも設立されて、25年を迎えた。ピンポン外交、統一コリア、南アフリカ組織の一本化など、国際平和への華やかな貢献の歴史の陰には、大学の枠を越えた同志的友情や連帯感が、表舞台に立つ役員たちを支えている。それは、一時期、同じ学生として自由に行き来し、切磋琢磨した体験と親近感がなせる業であろう。
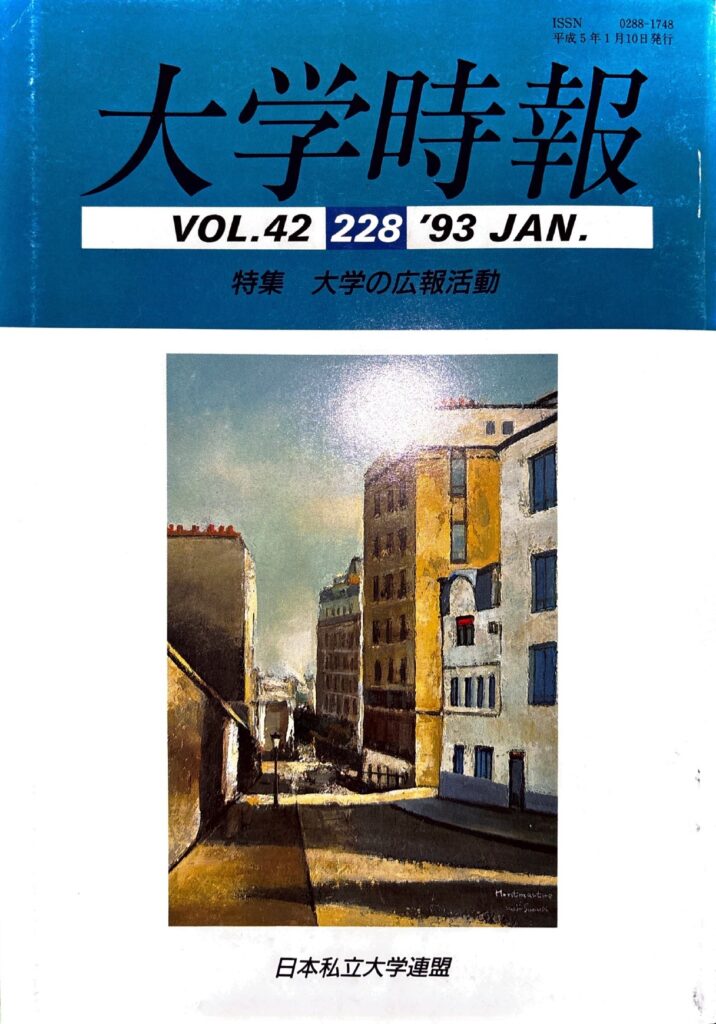
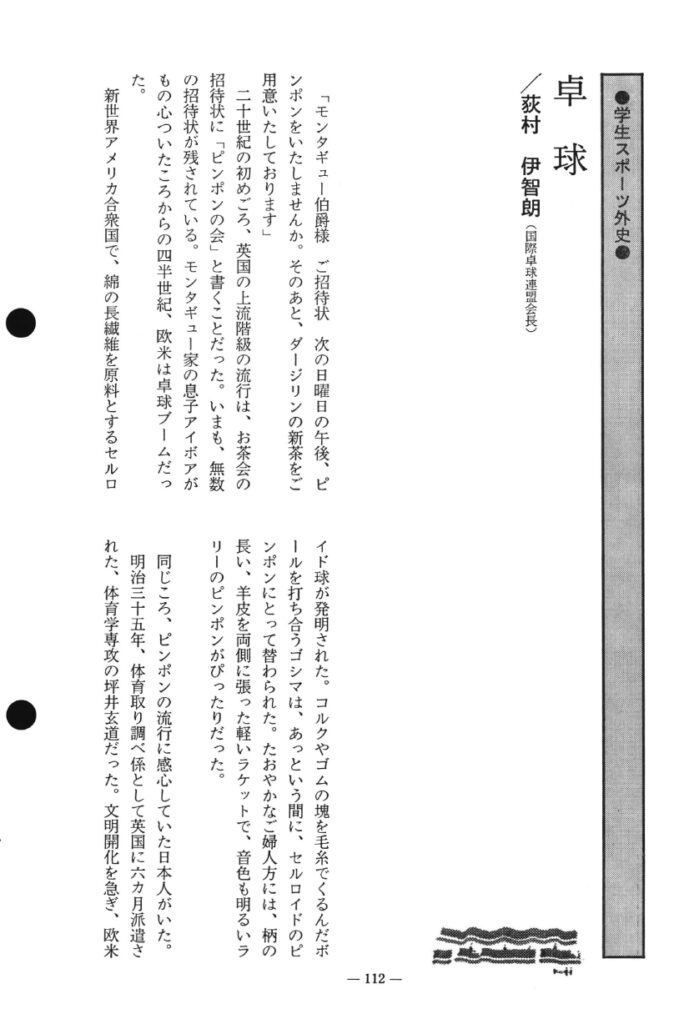
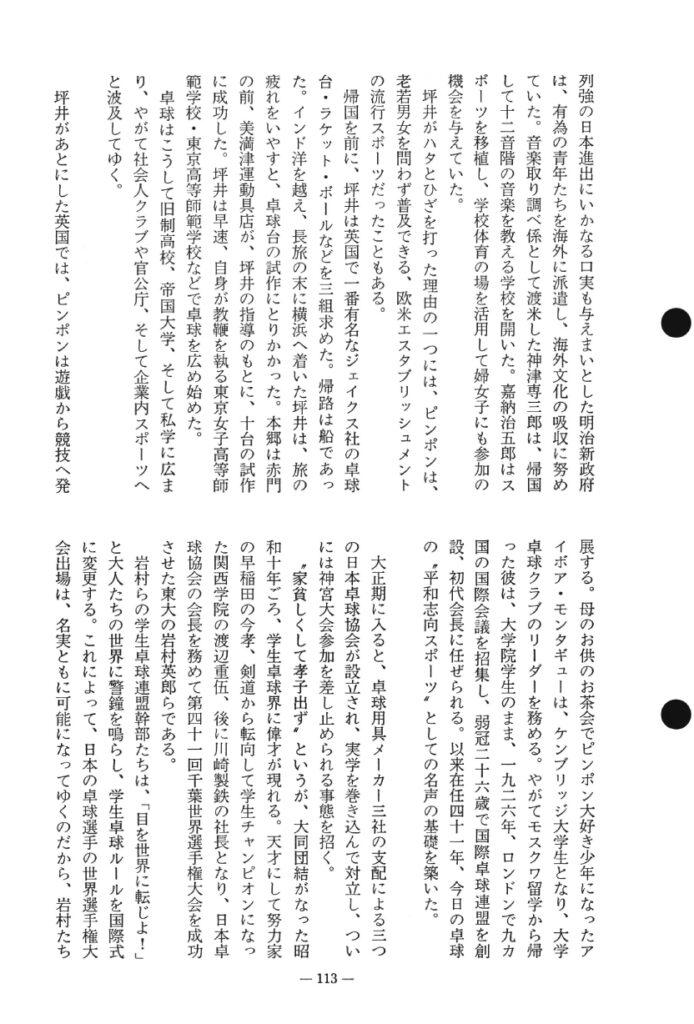
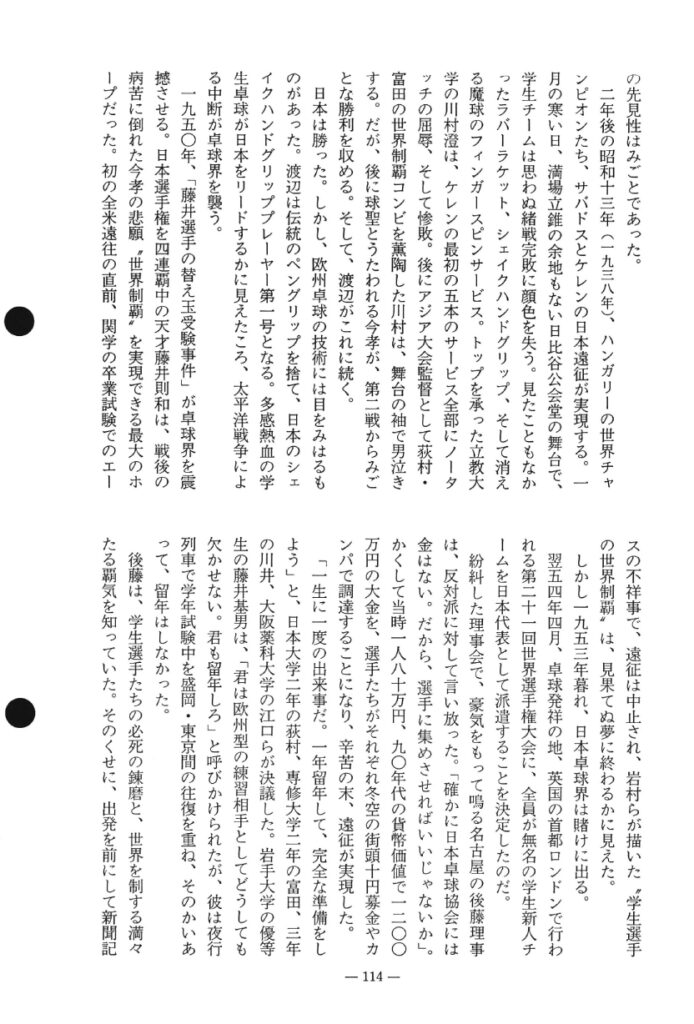
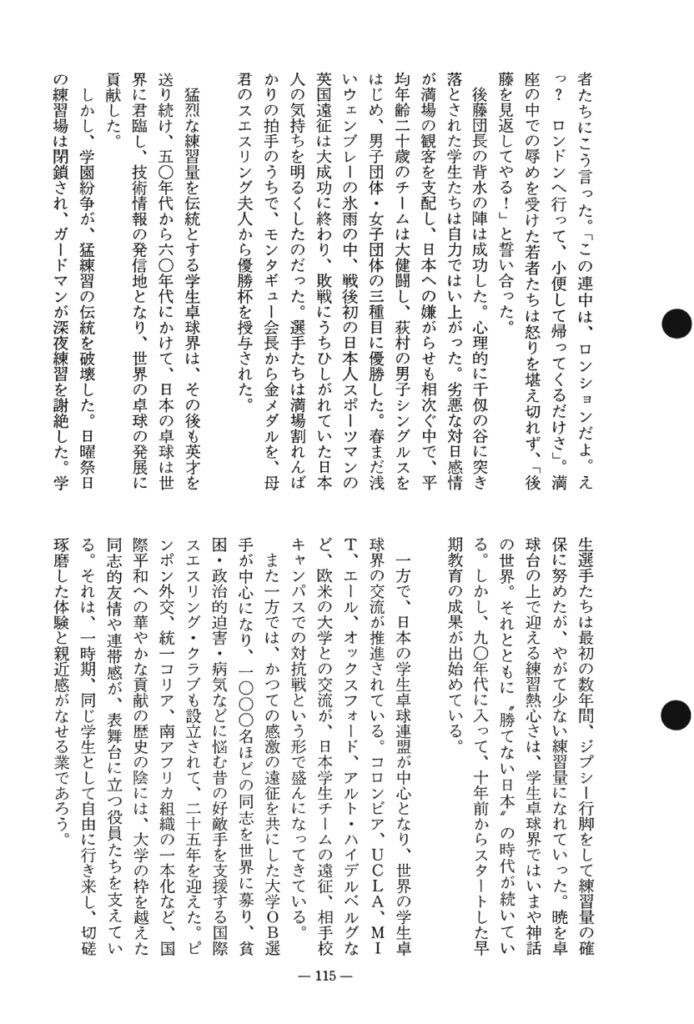
出典:日本大学私立連盟「大学時報」第228号 1993年1月号
URL:https://daigakujihou.shidairen.or.jp/list/contents/?jihou=228