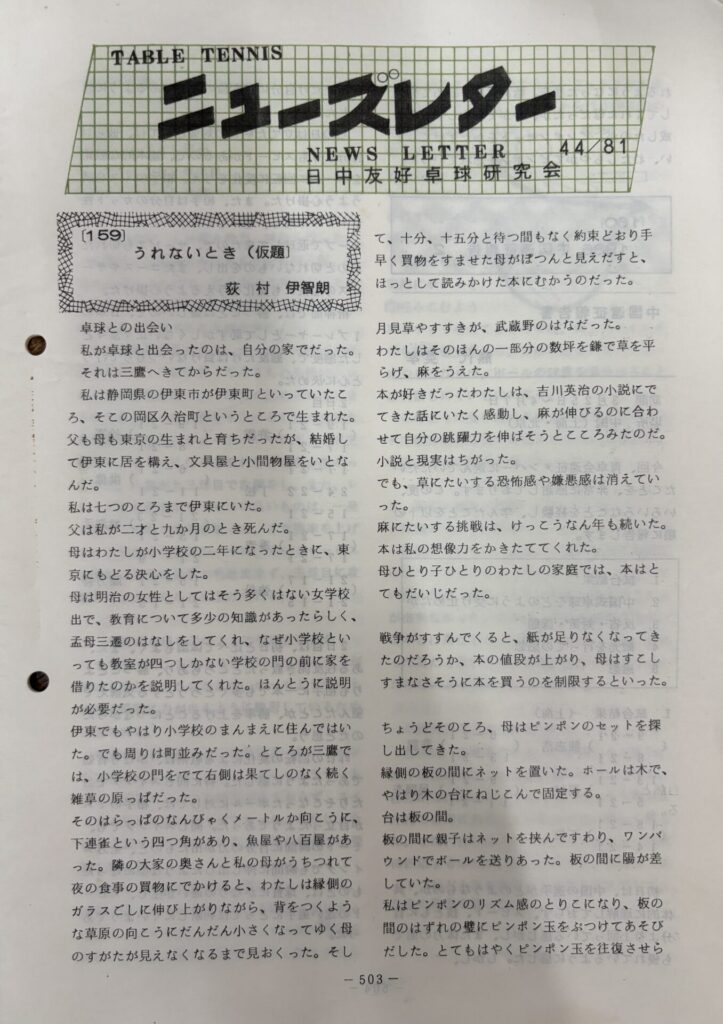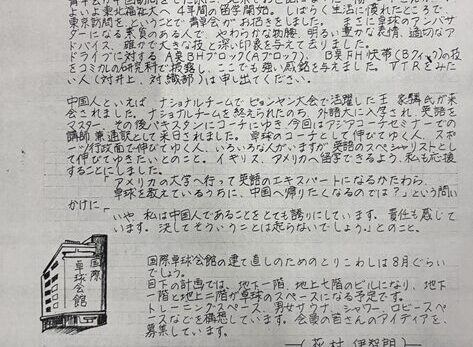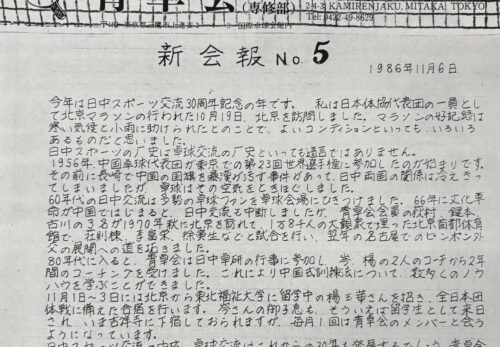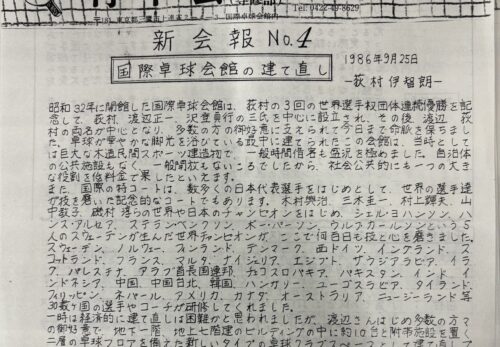ニューズレター
日中友好卓球研究会
荻村伊智朗
うれないとき(仮題)
卓球との出会い
私が卓球と出会ったのは、自分の家でだった。
それは三鷹へ来てからだった。
私は静岡県の伊東市が伊東町といっていたころ、そこの岡区久治町というところで生まれた。父も母も東京の生まれと育ちだったが、結婚して伊東に居を構え、文具屋と小間物屋をいとなんだ。
私は七つのころまで伊東にいた。
父は私が2歳と9ヶ月のとき死んだ。
母はわたしが小学校の2年になったときに、東京に戻る決心をした。
母は明治の女性としてはそう多くはない女学校出で、教育について多少の知識があったらしく、孟母三遷のはなしをしてくれ、なぜ小学校といっても教室が4つしかない学校の門の前に家を借りたのかを説明してくれた。ほんとうに説明が必要だった。
伊東でもやはり小学校のまんまえに住んではいた。でも周りは町並みだった。ところが三鷹では、小学校の門をでて右側は果てしのなく続く雑草の原っぱだった。
そのはらっぱのなんびゃくメートルか向こうに、下連雀という四つ角があり、魚屋や八百屋があった。隣の大家の奥さんと私の母がうちつれて夜の食事の買い物に出かけると、わたしは縁側のガラスごしに伸び上がりながら、背をつくような草原の向こうに、だんだん小さくなってゆく母のすがたが見えなくなるまで見おくった。そして、10分、15分と待つ間もなく約束通り手早く買い物をすませた母がポツンと見えだすと、ほっとして読みかけた本に向かうのだった。
月見草やすすきが、武蔵野のはなだった。
わたしはそのほんの一部分の数坪を鎌で草を平らげ、麻をうえた。
本が好きだったわたしは、吉川英治の小説にでてきた話にいたく感動し、麻が伸びるのに合わせて自分の跳躍力を伸ばそうとこころみたのだ。小説と現実はちがった。
でも、草にたいする恐怖感や嫌悪感は消えていった。
麻にたいする挑戦は、けっこうなん年も続いた。本は私の想像力をかき立ててくれた。
母ひとり子ひとりのわたいの家庭では、本はとてもだいじだった。
戦争がすすんでくると、紙が足りなくなってきたのだろうか、本の値段が上がり、母はすこしすまなそうに本を買うのを制限するといった。
ちょうどそのころ、母はピンポンのセットを探し出してきた。
縁側の板の間にネットを置いた。ポールは木で、やはり木の台にねじ込んで固定する。
台は板の間。
板の間に親子がネットを挟んですわり、ワンバウンドでボールを送りあった。板の間に陽が差していた。
私はピンポンのリズム感にとりこになり、板の間のはずれの壁にピンポン玉をぶつけてあそびだした。とてもはやくピンポン玉を往復させられるようになった私を、始めは目を細めて称賛してくれた母だったが、やがて熱中しすぎを警戒したのか、ピンポンセットをかたずけてしまい、わたしもやがてピンポンを忘れていった。
(つづく)