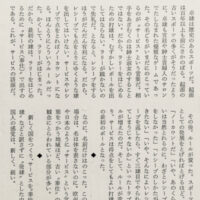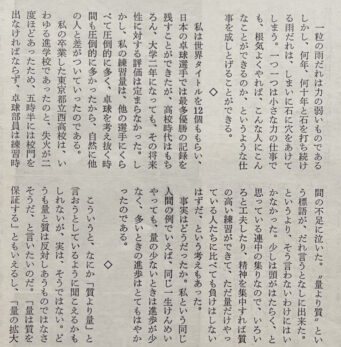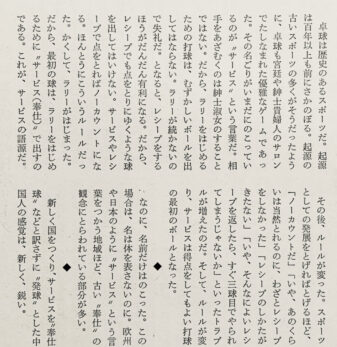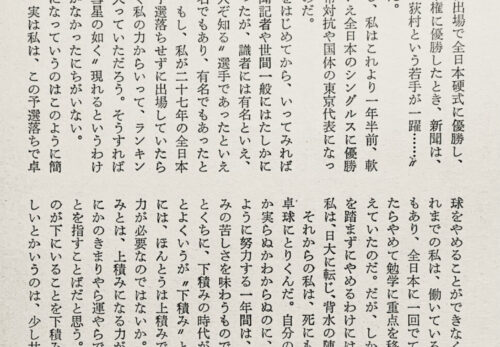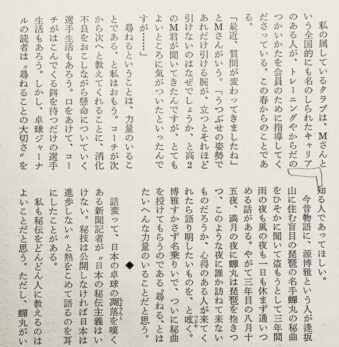<技術は道具に勝てない>という命題をあなたはどう思われるか。
賛成意見は次のようであろう。
「そうなのだ、人間の歴史は道具の歴史なのだ。そのために、力も生命力も弱い人間が地球の支配者になったのだ」
第二次大戦後、ほんとうにマッチのない時代があった。木をこすり合わせて火を起こしたり、レンズで太陽光線をうまく集めて火をつけたりする遊びが中学校ではやったが、これはきっと大人たちがそういうことを家でやったのを少年たちがみたからであろう。
“火種”といって、夜寝る前に炭火のまっ赤になったものを火鉢の灰にいけて眠った。しかし、マッチやライターがでまわれば、木をこすって火を起こす技術やレンズをうまく使う技術や、炭火を灰の中にうまくいける技術は忘れさられてしまう。
円周率を一生かかって計算した学者がイタリアだかフランスだかにいたそうだが、大型のコンピューターがあれば、この学者はもっといろんな研究に時間を使えただろう。
反対意見は、次のようであろう。
「人間は道具の奴隷になってはいけない。ある特殊の人だけしか使いこなせない道具であってはならない」
道具というと、すぐラケットを連想する必要はない。練習のシステムも道具である。強い選手が育つチームには、すぐれた道具としての練習システムがあるといってよい。日本には、いろいろな意味ですぐれた道具がある。卓球ジャーナルもその一つだ。
日本語の読める人がとても有利だ、とほんとうに思う。外国の選手が日本へつぎつぎと研修に訪れるのも無理はない。中国にも学ぶべきものが多い。
もし、日中戦を毎年やらなくなったら、日本の選手はもっとおくれているだろう。日本の選手といっても、たくさん練習をやる選手は、年間1500時間以上やっている。そうなると、中国の選手と練習量もそうちがいはない。
にもかかわらず、中国の15、16歳の選手に、日本の大人の選手がかなわない。日本の選手もたいへんまじめに努力をしている。関係者もいっしょうけんめいだ。なのに差がひらく一方なのはなぜか。
同じ一時間の練習効果を高める<道具としての練習のしくみ(システム)>を私たちがもっと改良しなければならないことを、78年の日中戦は教えてくれた。
1978年8月
荻村伊智朗

※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。
王国e Bookはこちら。