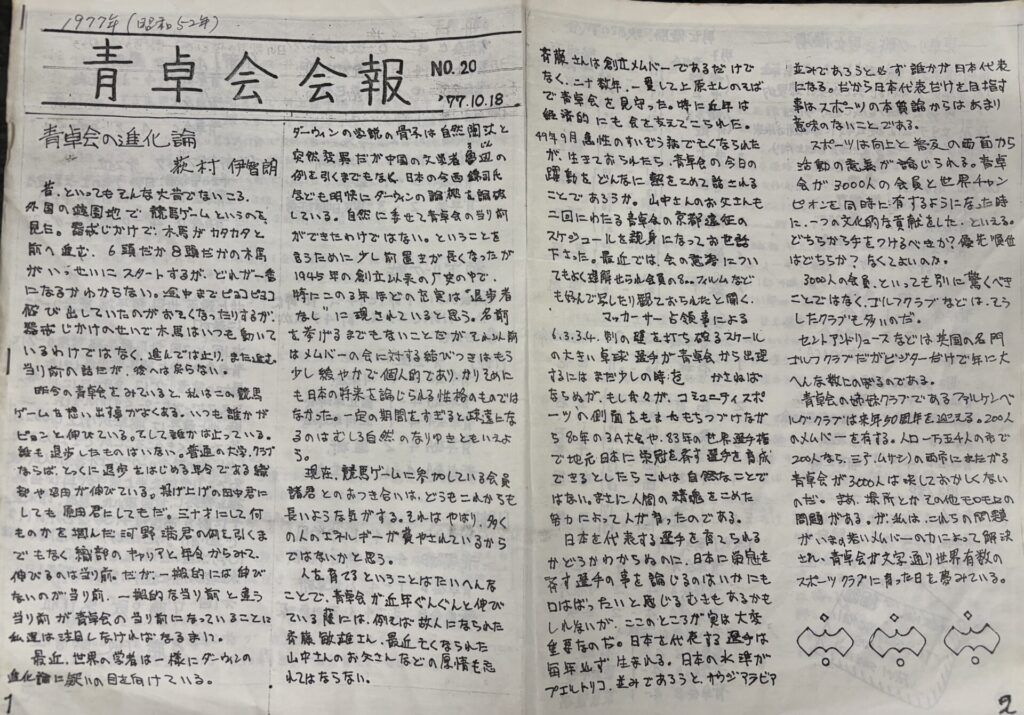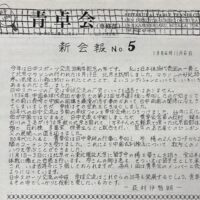青卓会の進化論
昔、といってもそんな大昔でないころ、外国の遊園地で競馬ゲームというのを見た。器械じかけで、木馬がカタカタと前へ進む。6頭だか8頭だかの木馬がいっせいにスタートするが、どれが一番になるかわからない。
途中までピョコピョコ飛び出していたのがおそくなったりするが、器械じかけのせいで木馬はいつも動いているわけではなく、進んでは止まり、また進む。当たり前の話だが、後へは戻らない。
昨今の青卓会をみていると、私はこの競馬ゲームを思い出すことがよくある。いつも誰かがピョンと伸びている。そして誰かは止まっている。誰も退歩したものはいない。
普通の大学、クラブならばとっくに退歩をはじめる年令である織部や沼田が伸びている。投げ上げの田中君にしても、原田君にしてもだ。30歳にして何ものかを掴んだ河野満君の例を引くまでもなく、織部のキャリアと年令からみて、伸びるのは当たり前。だが、一般的には伸びないのが当たり前。一般的な当たり前と違う当たり前が青卓会の当たり前になっていることに、私達は注目しなければなるまい。
最近、世界の学者は一様にダーウィンの進化論に疑いの目を向けている。ダーウィンの学説の骨子は自然淘汰と突然変異だが、中国の文学者魯迅の例を引くまでもなく、日本の今西錦司氏なども明快にダーウィンの論拠を論破している。
自然に委せて青卓会の当たり前ができたわけではない。ということを言うために少し前置きが長くなったが、1945年の創立以来の歴史の中で、特にこの3年ほどの充実は“退歩者なし”に現されていると思う。
名前を挙げるまでもないことだがそれ以前はメンバーの会に対する結びつきはもう少し緩やかで個人的であり、かりそめにも日本の将来を論じられる性格なものではなかった。一定の期間を過ぎると疎遠になるのはむしろ自然のなりゆきといえよう。
現在競馬ゲームに参加している会員諸君とのおつき合いは、どうもこれからも長いような気がする。それはやはり、多くの人のエネルギーが費やされているからではないかと思う。
人を育てるということは大変なことで、青卓会が近年ぐんぐんと伸びている蔭には、例えば故人になられた斉藤敏雄さん、最近亡くなられた山中さんのお父さんなどの厚情も忘れてはならない。
斉藤さんは創立メンバーであるだけでなく、二十数年、一貫して上原さんのそばで青卓会を見守った。特に近年は経済的にも会を支えてこられた。
49年9月急性のすいぞう病で亡くなくなられたが、生きておられたら、青卓会の今日の躍動をどんなに熱を込めて話されることであろうか。
山中さんのお父さんも2回にわたる青卓会の京都遠征のスケジュールを親身になってお世話くださった。最近では、会の意義についてもよく理解させられ、会員の8mmフィルムなども好んで写したり観ておられたと聞く。
マッカーサー占領軍による6.3.3.4制の壁を打ち破るスケールの大きい卓球選手が青卓会から出現するには、まだ少しの時を重ねればならぬが、もし我々がコミュニティースポーツの側面をもちつづけながら80年の3A大会や83年の世界選手権で地元日本に栄冠を斉す選手を育成できるとしたらこれは自然なことではない。まさに人間の精魂をこめた努力によって人が育ったのである
日本を代表する選手を育てられるかどうかわからぬのに、日本に栄冠を斉す選手のことを論じるのは、いかにも口はばったいと感じるむきもあるかもしれないが、ここのところが実は大変重要なのだ。
日本を代表する選手は毎年必ず生まれる。日本の水準がプエルトリコ並みであろうと、サウジアラビア並みであろうと必ず誰かが日本代表になる。だから、日本代表だけを目指す事はスポーツの本質論からはあまり意味のないことである。
スポーツは向上と普及の両面から活動の意義が論じられる。青卓会が3000人の会員と世界チャンピオンを同時に有するになったときに、1つの文化的な貢献をしたといえる。どちらから手をつけるべきか?優先順位はどちらか?なくてよいのか。
3000人の会員といっても、別に驚くべきことではなく、ゴルフクラブなどはそうしたクラブも多いのだ。
セントアンドリュースなどは英国の名門ゴルフクラブだがビジターだけで年に大へんな数にのぼるのである。
青卓会の姉妹クラブであるファルケンベルグクラブは来年50周年を迎える。200人のメンバーを有する。
人口1万5000人の市で200人なら、三鷹、ムサシノの両市にまたがる青卓会が3000人は決しておかしくないのだ。
まぁ、場所とかその他モロモロの問題があるが、私はこれらの問題が今の若いメンバーの力によって解決され、青卓会が文字通り世界有数のスポーツクラブに育った日を夢みている。
荻村伊智朗
1977年10月18日