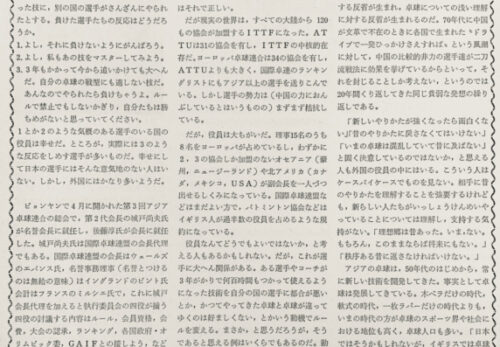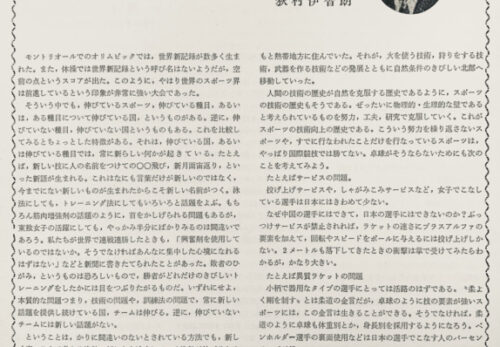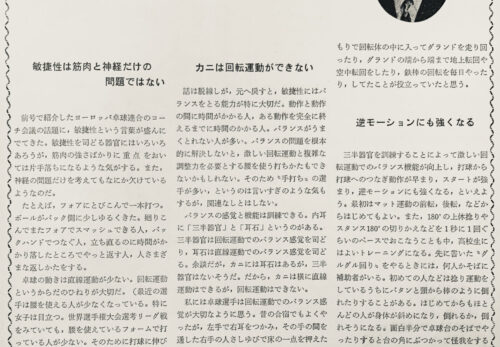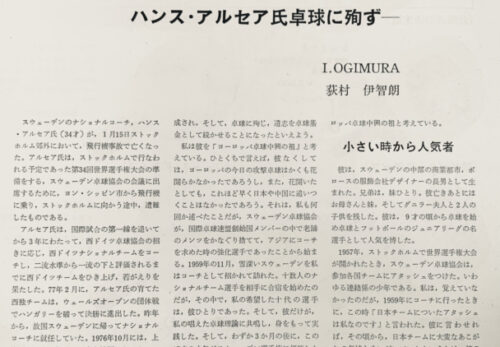卓球とオリムピック
オリンピックの季節である。卓球はノンオリムピック種目中の王者だ。123の加盟協会をもっていて、80カ国を一堂に集めるような大会を毎年開催する実力を発揮している。最近もある有力なIOC委員が、ブダペストのテレビインタビューで、「十数カ国のノンオリムピック種目のうち、卓球参加の問題は重要」と答えている。卓球とオリムピックについていくつか考えてみよう。
卓球はオリムピックに入らないのか、入れないのか両方である。むしろ前者の方が強い。卓球とオリムピックとの交渉をする窓口といえば、かたや国際卓球連盟(ITTF)かたや国際オリムピック連盟(IOC)ということになる。
ITTFの側からみれば、オリムピックにはいくつかの欠点がある。それで入らない。IOCの側からみれば、ITTFにはいくつかの難点がある。それでオリムピックゲームに加えにくい。
ITTFの事情を語るとき、そして歴史を語るとき、40年間会長をつとめたモンターギュ前会長のことをおとすことはできない。彼が今日の世界第3番目のIF(国際競技連盟)であるITTFをつくりあげた人なのである。
ITTFにも、IOCにも第一次大戦と第二次大戦の深刻な人類の葛藤に学んだ態度が現われている。ITTFは戦争をあおりたてる一つの側面となったナショナリズムをできるだけ表面からは押さえる側に座って、今日の123カ国の大所帯を築き上げてきた。世界選手権大会の表彰式において、国旗、国歌がないことはその現れなのである。
ITTFの歴史から言わせれば、IOCには、ベルリンオリムピックがヒットラーナチスの示滅の場としてふんだんに利用された過去の不手際に対する現実的な反省の態度がなかった、ということになる。いっぽう卓球の方は、無用な摩擦を最大限に避けることによって、政治的、軍事的には敵対する国と国との間に専ら競技の交換を最大限に可能にさせてきている。
この点、目立たないことだが、国旗、国歌を使わない卓球と、国旗がメーンポールにいくつ立ち、毎日のメダルが国別に集計されていくオリムピックとは、態度にの違いがあるのである。
だから、ほんとうは卓球のユニフォームは無地であり、国章をつけたりはしない。中国はこうしたルールをよく守っている。日の丸を胸につけたがる私たち日本は、ややナショナリズムを持ちこむ方であろう。
次にプレイヤーの問題がある。オリムピックはいまやアマチュアという言葉を薄めてゆきつつある。一種の精神規範としてのアマチュアリズムは、今後も命を絶やすことはあるまいが、「車夫、馬丁、郵便配達人は競技会に出てはいけない」にはじまった身分規定としてのアマチュアリズムは力を失い、オリムピック大会への参加規定という形で、プレイすることや、名声を利用することによって金銭を得るものが参加できないようになってきた。
卓球にはもう一歩すすめて、アマチュアとプロフェッショナルを色別する考え方がない。バイオリニストや画家と同じで、金がとれるほどうまくなった人も、下手で金がとれない人も、世界選手権大会に参加するときは同じ資格の“プレイヤー”である、とわりきっている。
ただし、世界選手権大会でのプレイを対象にして、いっさいの金品の授受をおこなってはならない、とされている。プレイやプレイの成績を対象とし、金品を日常受けとっているかどうかという基準からみたり、卓球以外に仕事をしているのかどうか、という点からみれば、欧州の一流選手は男女上位50人ぐらいまでは、西欧も東欧も、卓球によって生活している人たちといってよかろう。
この点は、IOCの側からみれば、ITTFの最大の難点と見えるのである。
ところが、プレイヤーである考え方は、50年の卓球の歴史を経て、いまやテニスの世界に移植され、サッカーやいろいろな競技がこの考え方に習おうという傾向が生まれてきている。
ITTFの側の鋭いみかたを紹介すれば、古代オリムピックの純粋アマチュアは、実は奴隷制度の上に立った人力がなくても、金の入ってくる貴族制度の上にはじめて成り立ったものであった。
それが近代オリムピックとして復興できたのも、イギリスやフランスなどの上流階級・貴族階級が基盤であったからで、大衆・庶民はスポーツをしないもの、身分の卑しいもの、貪しいものはクラブのメムバーになれないもの、という制約の上に成り立ったのだというのである。
古代オリムピックが崩壊したのは、貴族が自らプレイするのをやめて、奴隷に代理戦争をやらせるようになったからである。近代オリムピックや、近代スポーツの抱える問題は奴隷がスポーツをやる問題ではなく、自由人としての貧乏な大衆がスポーツをするようになったことである。
ここに、旅費や練習費、生活費の問題が生じてくる。働かねば食えない人がスポーツをするのと、働かなくても食える人がスポーツをするのとでは違いがあるのは当然のこと。社会主義制度の国家では、国が選手の面倒をみるのが当然ということになっていく。
古代オリムピックが崩壊したときと、近代オリムピックが難問をかかえて四苦八苦している状態とを重ならして理解しようとするのは、見方としてうまくいくまい。
歴史発展の過程で、奴隷制度の時代と現代とを同列において論じれば、純粋なアマチュアを生ぜしめるためには、貴族によるスポーツの独占が必要となってくる。これは歴史の歯車を逆転させようとする発想法である。
今日のスポーツ人口の多数を占める庶民は、こうした成り行きが生ずれば反対するに違いない。だれでもいったん手に入れたものは奪われたくないものである。
ITTFからみての第3のIOCの難点は中国代表権の問題である。第二次大戦終了直後、北京のNOCは、ローザンスに電報をおくり、中華人民共和国NOCが今後中国国内のオリムピック運動を代表する旨を伝え、これは受理された。ところが、ずいぶんたってから、いかなる手違いか、台湾からの転居通知が重ねて受理され、IOCは二つの中国を認める事務上と政治上の誤りをしてしまった。中国がこれに抗議して、代表権の正当な回復を主張しつづけて、20数年もたってしまった。
カナダ政府は、台湾チームが中国を代表する名称や記章をつけて参加しようとした場合入国を認めない、という態度を打ち出した。
日本でオリムピックをやれば、日本国政府も同じ態度に出ることであろう。これにIOCの関係者があちこちで“政治が介入”といって非難をした。
カナダ政府に言わせれば、それは20数年前にIOCが犯した事務上のミスをあらためようとしないからである。
政治的理由があってミスをあらためようとしないのだろう、ということになるのである。
ITTFはこの点、この種の問題は最小限度にしか生じてきていない。ITTFのモンターギュ前会長はさめた眼で歴史を見てきた。古代ギリシャのスポーツ以来、スポーツが政治制度と関係ないことなどはいまだかってなかったのである。それならば、避けるのではなく、積極的にとりくむことである、というのは前会長の態度であった。もし、ITTFがいまのIOCは突然参加を請われたとしても、ITTFはこうした3つの難点にクレームをつけることになるだろう。同時にそれは、IOC側からITTFをみた際の難点である。日本の体協やジャーナリズムでも、名古屋のピンポン外交当時も、“なんだい卓球のやっていることは?”という声があった。しかし、故後藤会長はスポーツ人として前人未踏の勲二等をもって国からその功績をたたえられたのである。
しかしながら、実はITTFはIOCと加盟についての接触を続けている。それは、IOCに対してではなく、IOCの傘下の各NOCに対しての各国レベルでの各国卓協の加盟を認めるかどうかの話し合いである。
これが3つの難点についてのITTFの卓則的な態度を曲げることなく、各国毎に解決されれば、123の加盟協会中の半数は予算を急増させることができるのである。
1976年6月
荻村伊智朗


※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。
王国e Bookはこちら。