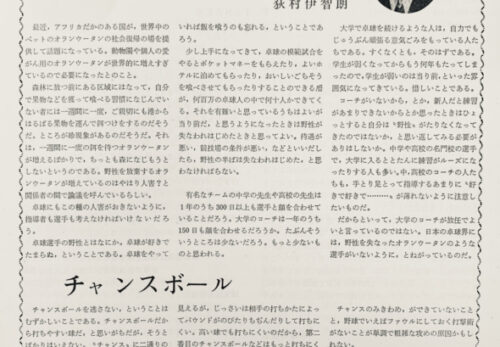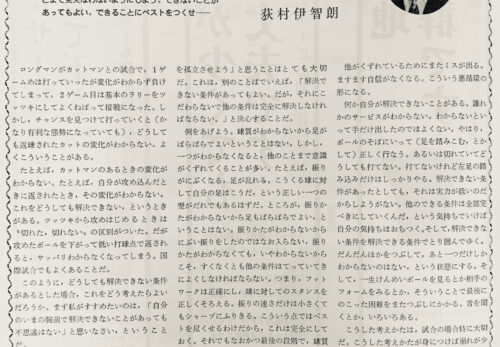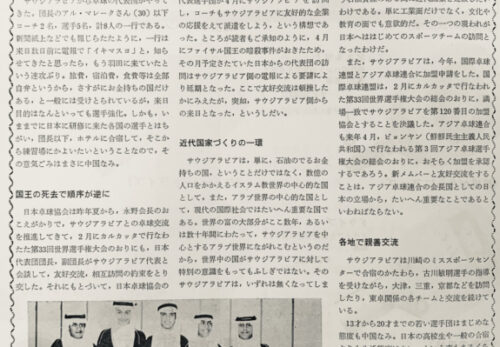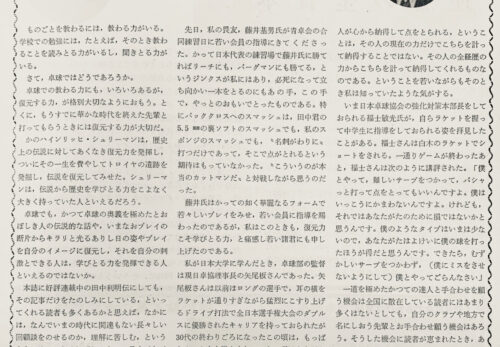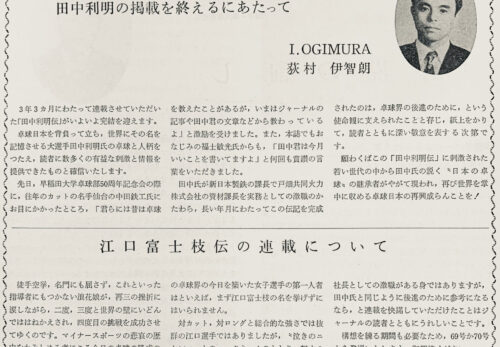無題
カルカッタ世界選手権の年が終わろうとしている。もちろん、バーミンガム大会は、もうはじまったといえる。
先般、伊豆の大仁でおこなわれた体協とJOC主催のコーチ研修会で大島鎌吉氏が特別講演をされ、その中でミュンヘンオリンピックの8カ月前の期間の使いかたにふれられた。オリンピック代表選手によくみられる例として、各国とも4カ月ぐらい前に予選があり、それが終わると一時的に調子が落ちる例が多いという。特に日本だけではなく、外国にもよくその例が見受けられるとのこと。考えられる原因としては、オリンピック予選で自分の力を出しつくしてしまい、代表になるともう発揮する精神的、肉体的パワーがなくなる場合がけっこう多いのだそうだ。
卓球の場合を考えてみても、国内の試合と国外の試合との調整には苦労がある。いまのように、間に2年もあると、少し息をつく暇があるが、54~59年迄の5年間は、毎年日本選手権と世界選手権があり、私たちは毎年すべての国内行事と世界選手権を消化することを要請された。
日本チャンピオンや世界チャンピオンの責任として、日本の卓球を盛んにするのには自分のからだを動かして貢献せねばならない。ムリな遠征や試合を重ねたため、けいれんをやったり(後にこれは後遺症的に再発して冬の全日本では苦しめられた。)黄だんになったりしたが、他人がその苦しさをわかってくれるものではない。
私の例でいえば、私がただ単なる卓球キチガイから脱して、死にものぐるいの練習にとりくんだのには動機があった。52年のリーチとバーグマンの来日により、15戦全敗の屈辱的な全日本軍の試合を目のあたりに見たことである。「だれもやれないのなら、よーし、俺がやらねば!」ただそれだけのことである。
だから、あくまで目標は世界へ出かけて行って勝つことであり、国内行事の成績よりは、国際行事の成績をあげるべく努力したのは当然である。打法も、当然のことながら、世界史上超弩級といわれる当時のシド、バーグマン、リーチ、マイルズ、アンドレアディスらに勝つように工夫し、改造したのである。
全日本で良い成績をあげ、日本代表になることは、世界への一里塚であり、当然通らねばならないきわめて重要なチェックポイントであったが、日本の球界のために世界を征するという観点からみればゴールではない。だから、日本代表になってから世界を目ざしての練習に切りかえる、ということはなかった。三百数十日をかけて、次の対シド、バーグマン、リーチ、アンドレアディスらとの一発勝負に備えるのであるからだ。
これは別に私だけの話ではない。私たちのような、はじめて遠征にいった世代は、ほとんどそうだった。そして、東京大会あたりで、日本の名声は確立した。どんなにきわどい勝利でも三度つづけばまぐれとはいいきれない。当然のことながら、日本卓球界が“日本を制するものは世界を制する”という気分になってきた。このことには良い面と悪い面がある。
悪い面の一例として、東京大会以後の世代の選手をみていると、世界選手権日本代表=ボーナス、という考えが少しづつ日本代表選手の中に入りこんできたのである。アメリカなどは、完全にこうした考えかたである。中国には、全くこうした考えかたはないようだ。
世界選手権日本代表=新しい責任の追加、という観点になると、選ぶ者も選ばれるものも、当然そうした意識でとりくむようになるが、代表は日本選手権をはじめとする各試合の成績に対するボーナス、という気持ちになると、「代表にまずなりたい。代表になったらベストを尽します」という言葉はでてくるが、「代表になったからには勝ってきます」という言葉はなかなかでてこない。
50年11月のはじめ、菊薫る文化の日、卓球界から三人の先輩が卓球の発展につくした功績をたたえられて国から表彰を受けた。
山本弥一郎(勲四等)、竹原英太郎(藍綬褒章)、長谷川喜代太郎(藍綬褒章)の三氏である。
三人の先輩の功績の詳しいことについては本欄ではふれない。一つだけいいたいことは、マイナースポーツ卓球を背負って立った草分けの人たちだ、ということだ。
卓球が今日のように陽の当たるスポーツでもなく、自ら卓球台をリヤカーで会場へ運び、受け付けをやり、進行をやり、選手として試合をやり、表彰をやり、記録をつくり、新聞社にたとえ3行でもよいから記事を書いて下さいと頼んで回って大会をやってきた人たちである。
この中には、私たちがロンドンで団体戦の決勝ポイントをあげたとき、感激のあまり大きな日の丸の旗を振ろうとした人もいる。この人たちが世界選手権にのぞみ、卓球の興亡をそれに賭ける気持ちには私たちと共通する背景があったように思える。それはマイナースポーツの悲哀を身にしみて味わっていたことである。
日本の卓球が再び世界でコンスタントに勝てるような実力を持つためには、少し極端ないいかたをすれば、その民族の興亡を荷うぐらいの気迫がなければなるまい。まして、中国が文化大革命のブランクからカムバックしつつある今の時代の卓球界は、ようやく競争らしい競争時代になってきた。
この文章がお手許に届くころには日本選手権も終わり、新しい日本チャンピオンが誕生しているかもしれない。心して、新しい時代のリーダーになって責任を果たしてもらいたい。
マスコミが全く歯牙にもかけない時代に逆もどりしないためには、なんといっても強くなければならないのである。
また、将来の日本チャンピオンを目ざす人たちも、そのあとには、更に大きな仕事が生じるのだ、ということを自覚してやっておくことをお推めしたい。それでこそ、バーミンガムやアメリカで、立派な成績が生まれ、本人も卓球界もニコニコ顔になれるのだ。負けて帰ってくる日本代表になるのは、あまりおめでたい話ではないのだから。
繰り返して申し上げることをお許しいただきたいが、チャンピオンシップや、日本代表はボーナスや権利ではない。責任である。よーし、僕が、私が、その責任を果たしてやろうという意気高らかな後輩の出現を大いに期待している。
1975年10月
荻村伊智朗
※注:執筆当時の時代背景を考慮し、原文をそのまま掲載しています
-834x1024.jpg)
※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。
王国e Bookはこちら。