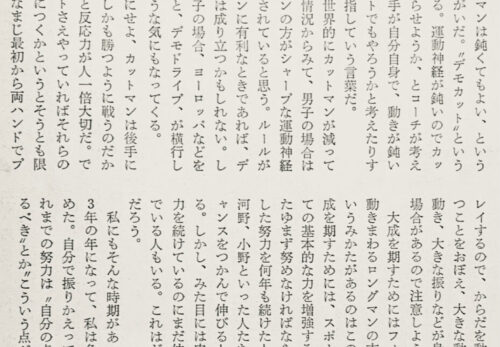雑誌の功罪
私たちが高校生のころ、指導書といえば今孝氏の『卓球』と福士敏光氏の『卓球』であった。
これらの本がいまの指導書とちがうのは、写真がきょくたんに少ないことだった。シャッタースピード25分の1秒くらい、しぼり8ぐらいでうつす写真だから、たいてい屋外で撮影してあり、しかも“コマどめ”であった。
つまり、写真のぬしがバックスウィングのところで動きをとめ、インパクトのところで動きをとめてみせる写真である。写真、というよりはイラストレーションにちかい性質をもっていた写真を私はみた。
私はもちろん、この写真からいろいろと想像し、文中の意味を移して動きをつけてみたりしてフォームをつくっていった。私の高校にはコーチがなく、上級者が指導してくれたが、自分自身で考えることはどうしても必要だった。
いまとなってみると、こうしたイラストレーション風の写真には数々のすぐれた点が多いことがわかってきた。実際の連続写真では動いているボールにあわせたりする姿勢が含まれるため、かならずしも理想的なフォームとはいえない。
また、そのひとが自分の“感覚”で正しい、と思っているフォームとはちがうときがある。そんなとき、その名人が“理想”と思っているフォームをみたほうが役にたつ。連続写真といっても、写真には平面的な限界もある。また今日のように、卓球のコーチングもある程度の水準になればだれでもやるようになれば、誤解も多くなる。
そんなことを痛感したのは、ことしにはいって三回のスペシャライズド研究会を卓球ジャーナルの愛読者とやってみた結果だ。気の毒、といってはなんだが、独習・独学するひとにとっていままで出ている情報が、ひとりよがりなフォームづくり卓球づくりをさせる結果になりがちなのだ。
“中国型の打法にはバックスウィングがない”とか“バックスウィングが小さい”というが、はたしてそうだろうか。荘や徐・李らのフォームを分析してみても、私にはかならずしもそうは思えない。ところが、“ない”という観点から証拠写真を並べようとすれば、もちろん並べたてることができるのが印刷物のおそろしいところだ。
情報の質というものは、器機や器材によって決定されるものではない。この現象をどうみるのか、によって決定される。
1979年9月
荻村伊智朗
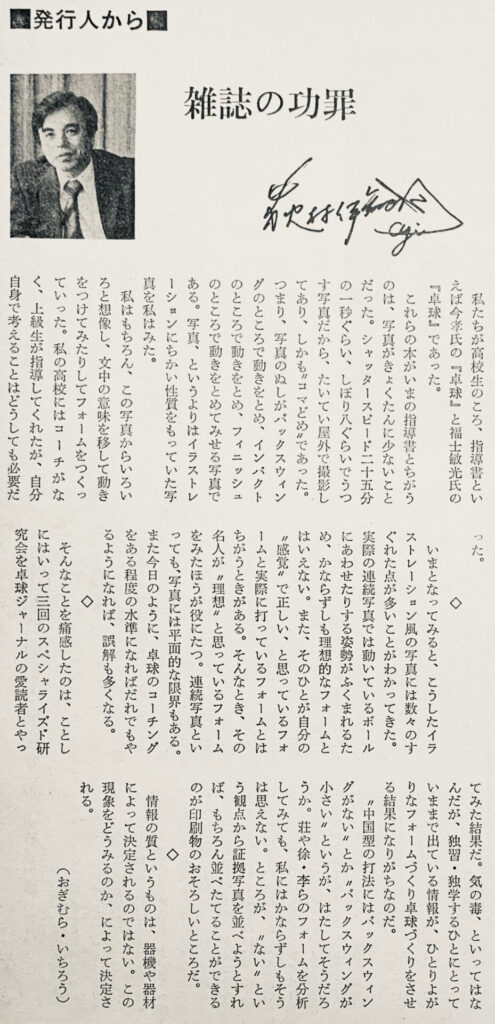
※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。
王国e Bookはこちら。

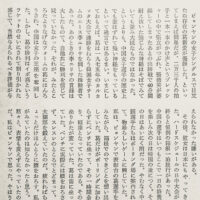
の深み-200x200.jpg)
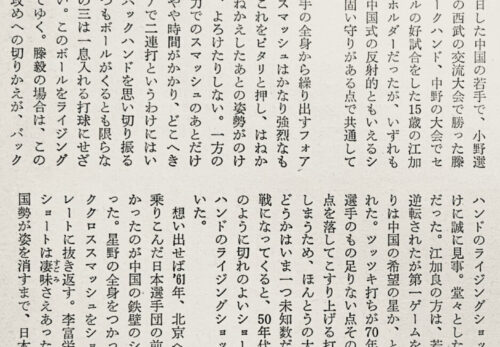
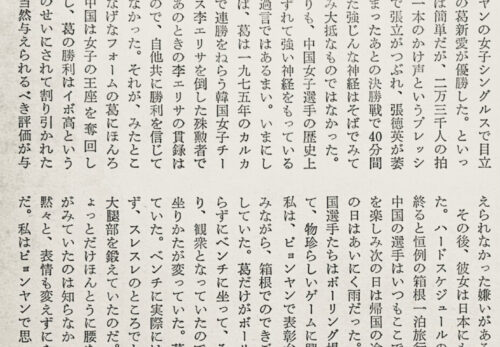
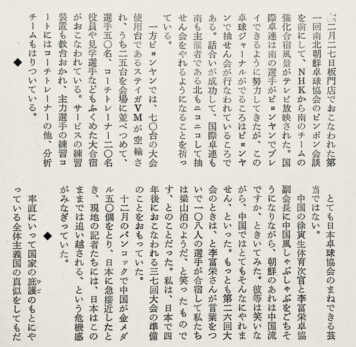
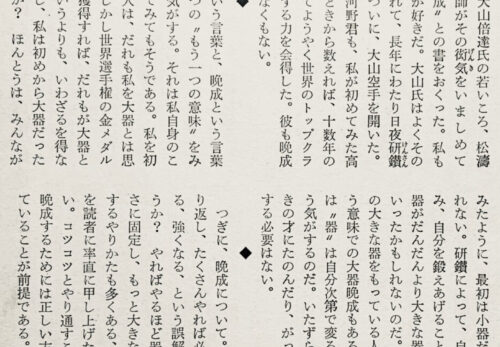
の深み-500x347.jpg)