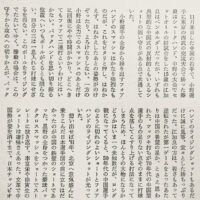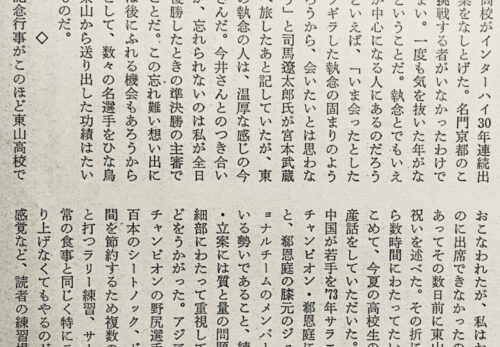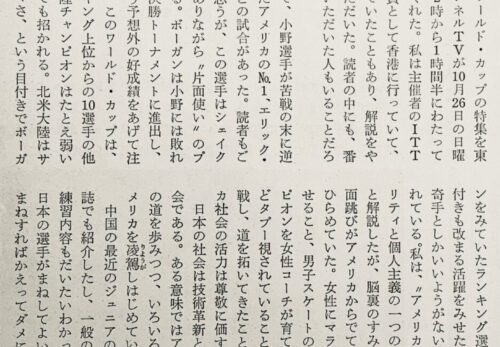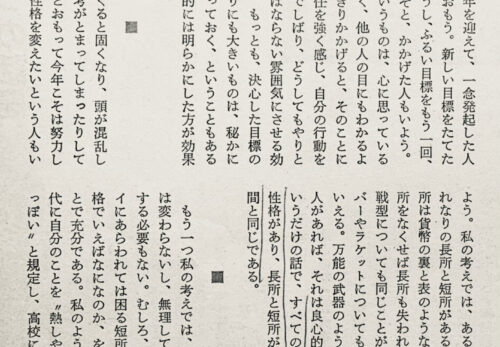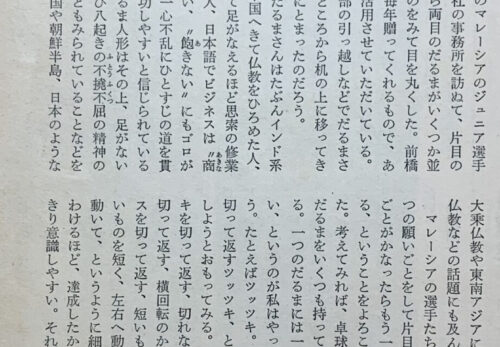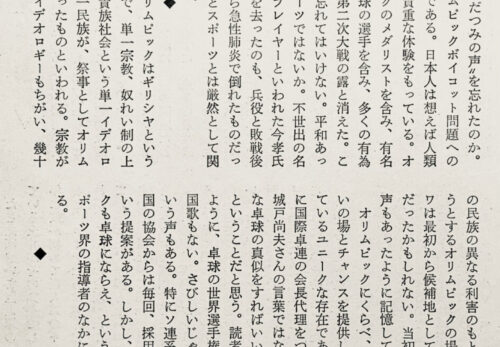無心
1979年12月の全日本決勝は、片面イボ高に変えた高島君が二連勝を飾った。女子で優勝した和田君もアンチに変えてからわずかの日数での優勝だ。
使いなれたラバーでもなかなか優勝できない。だから、変えてすぐ優勝したりするのをみると、つい、“用具戦争”などと口走りたくなるのも人情だ。しかし、冷静に考えてみると、変えてすぐ試合をやれば、うまくいかない例が9割以上であることは事実だ。だから、成功者には、そのときその用具に出会う歴史的必然性があったと考えてもよい。
何年ものあいだ、一つの用具で研さんを積む。あるところで行きづまる。伸び悩む。自分の体の条件、卓球の構造など思いあぐねた末に、考えに考えてここに至る。それがピッタリくるとすれば、むしろ必然の成功といえよう。歴史上、そのような成功者は多い。
転機をつかむ、ということは、精神を整理し、集中させるものだ。ラバーを変えると、新しい技法、新しい戦術のシステムを新鮮な気持ちで整理しておぼえこむことになる。あれもできる、これもできる、ということでなく、あれもできない、これも難しい、といった状態の中で、“これならできる”、“これを忘れまい”、といった形で新しく強い記憶が体の中にビルトインされてゆく。だから、割りきって、迷いなく、無心のプレーにつながりやすい。
決勝終了後のインタビューで、「勝つことは意識しなかった」「一球一球よいプレーを」「ここまでくるとは思わなかった」などと和田君がいっていたのは、彼女の無心の勝利を表現している。
高島君の勝利は裏がえせば小野君の敗北だ。小野君の敗北は、いわば無心の敗北とでもいえようか。
“無心の勝利”がピョンヤン大会の成績を小野君の側からみたものだとすれば、79年全日本は“無心の敗北”とみる。
なにごとでも徹底した態度になればなるほど両刃の剣のようなもので、おのれも傷つくことがある。無心なるがゆえの勝利と無心なるがゆえの敗北とはコインの両面だ。小野君の持ち味はこうした淡白な勝負観によって説明されるかもしれない。「僕にはまだまだやることがある」という彼の今後に期待しよう。
1980年1月
荻村伊智朗
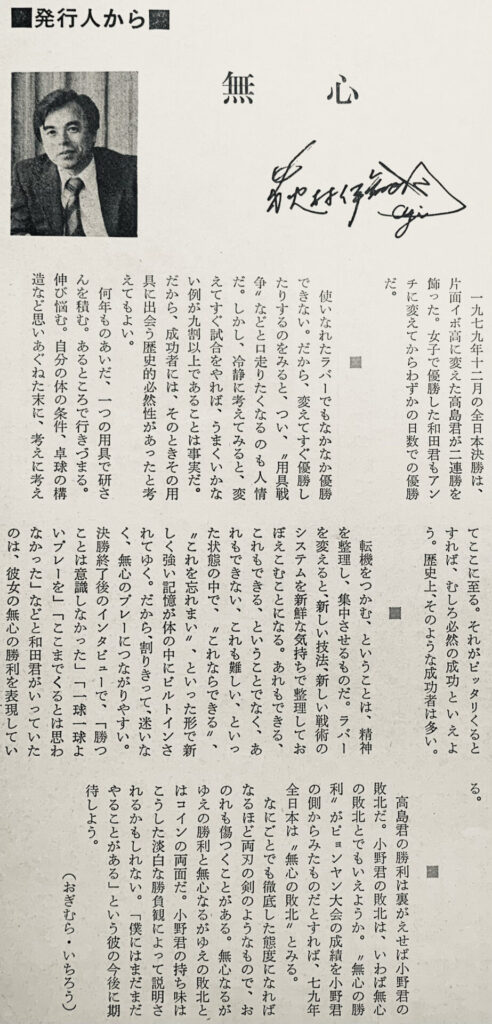
※卓球王国が運営する「王国e Book」では卓球ジャーナルの電子書籍を購入することができます。
王国e Bookはこちら。