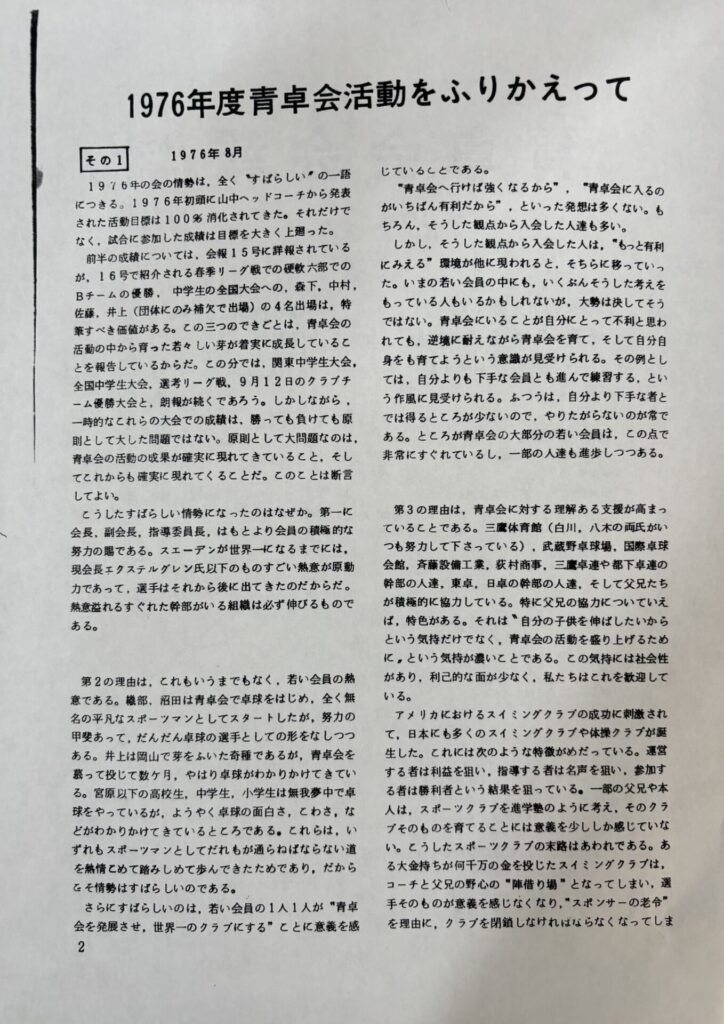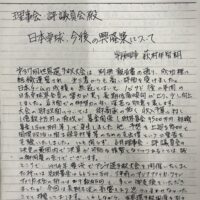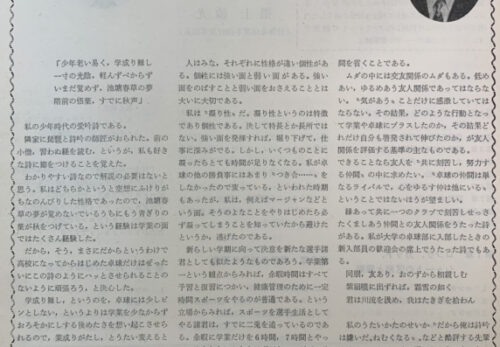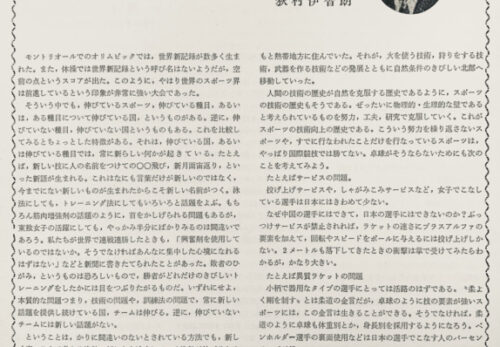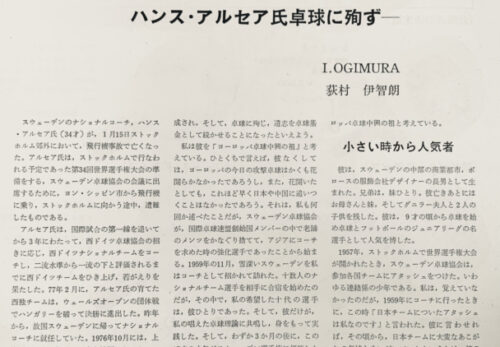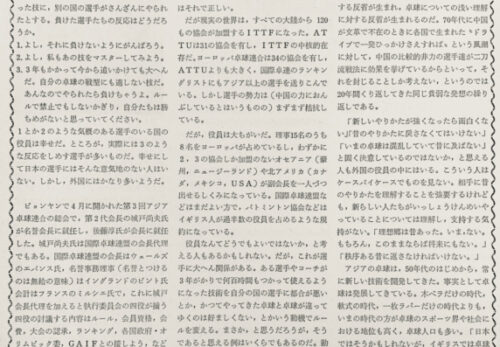1976年度青卓会活動をふりかえって
1976年12月
荻村伊智朗
1976年の会の情勢は、全く“すばらしい”の一語につきる。1976年に山中ヘッドコーチから発表された活動目標は100%消化されてきた。それだけでなく、試合に参加した成績は目標を大きく上廻った。
前半の成績については、会報15号に詳報されているが、16号で紹介される春季リーグ戦での硬軟六部でのBチームの優勝、中学生の全国大会への、森下、中村、佐藤、井上(団体にのみ補欠で出場)の4名出場は、特筆すべき価値がある。
この3つのできごとは、青卓会の活動の中から育った若々しい芽が着実に成長していることを報告しているからだ。
この分では、関東中学生大会、全国中学生大会、選考リーグ戦、9月12日のクラブチーム優勝大会と、朗報が続くであろう。
しかしながら、一時的なこれらの大会での成績は、勝っても負けても原則として大した問題ではない。原則として大問題なのは、青卓会の活動の成果が確実に現れてきていること、そしてこれからも確実に現れてくることだ。このことは断言しよ良い。
こうした素晴らしい情勢になったのはなぜか。第一に会長、副会長、指導委員長、はもとより会員の積極的な努力の賜である。
スウェーデンが世界一になるまでには、現会長エクステルグレン氏以下のものすごい熱意が原動力であって、選手はそれから後に出てきたものだからだ。熱意溢れるすぐれた幹部がいる組織は必ず伸びるものである。
第2の理由は、これもいうまでもなく、若い会員の熱意である。織部、沼田は青卓会で卓球をはじめ、全く無名の平凡なスポーツマンとしてスタートしたが、努力の甲斐あって、だんだん卓球の選手としての形をなしつつある。
井上は岡山で目を吹いた奇種であるが、青卓会を慕って投じて数ヶ月、やはり卓球が分かりかけてきている。
宮原以下の高校生、中学生、小学生は無我夢中で卓球をやっているが、ようやく卓球の面白さ、こわさ、などがわかりかけてきているところである。
これらは、いずれもスポーツマンとして、誰もが通らねばならない道を熱情こめて踏みしめて歩んできたためであり、だからこそ情勢はすばらしいのである。
さらにすばらしいのは、若い会員の一人一人が“青卓会を発展させ、世界一のクラブにする”ことに意義を感じていることである。
“青卓会へ行けば強くなるから”、“青卓会に入るのがいちばん有利だから”、といった発想は多くない。もちろん、そうした観点から入会した人たちも多い。
しかし、そうした観点から入会した人は、“もっと有利に見える”環境が他に現れると、そちらに移っていった。今は若い会員の中にも、いくぶんそうした考えを持っている人もいるかもしれないが、大勢は決してそうではない。
青卓会にいることが自分にとって不利と思われても、逆境に耐えながら青卓会を育て、そして自分自身を育てようという意識が見受けられる。
その例としては、自分よりも下手な会員とも進んで練習する、という作風に見受けられる。ふつうは、自分より下手なものとでは得るところが少ないので、やりたがらないのが常である。ところが、青卓会の大部分の若い会員は、この点で非常にすぐれているし、一部の人たちも進歩しつつある。
第3の理由は、青卓会に対する理解ある支援が高まっていることである。三鷹体育館(白川、八木の両氏がいつも努力してくださっている)、武蔵野卓球場、国際卓球会館、佐藤設備工業、荻村商事、三鷹卓連や都下卓連の幹部の人たち、東卓、日卓の幹部の人たち、そして父兄たちが積極的に努力している。
特に父兄の協力についていえば、特色がある。それは“自分の子供を伸ばしたいからという気持ちだけでなく、青卓会の活動を盛り上げるために”という気持ちが濃いことである。この気持ちには社会性があり、利己的な面が少なく、私たちはこれを歓迎している
アメリカにおけるスイミングクラブの成功に刺激されて、日本にも多くのスイミングクラブや体操クラブが誕生した。これには次のような特徴がめだっている。
運営するものは利益を狙い、指導するものは名声を狙い、参加するものは勝利者という結果を狙っている。一部の父兄や本人は、スポーツクラブを進学塾のように考え、そのクラブそのものを育てることには意義を少ししか感じていない。こうしたスポーツクラブの末路はあわれである。ある大金持ちが何千万の金を投じたスイミングクラブは、コーチと父兄の野心の“陣借り場”となってしまい、選手そのものが意義を感じなくなり、“スポンサーの老令”を理由に、クラブを閉鎖しなければならなくなってしまった。
「野球なら親たちが嫌がる子供をやらせたがるが、卓球じゃ親たちがそれほど夢中にならないのが普通」(勝山市のある中学校の先生)だが、卓球にだって、数は少なくても“野球パパみたいな親だっているのである。
青卓会は決してそのようなスポーツクラブのあとは追わないのである。また、スポーツ教室というのがあって、受験勉強の間にいかに効果的に運動して、健康を維持するかという発想での組織である。青卓会は、これらのいずれのまねもしない。
ありがたいことに、現在までのところ、父兄の理解は我々の立場からみて正しい方向に発展している。(もちろんお金はいくらでも出すから、うちの子供を教えて)という人もずいぶんいた。これからも出現するだろう。しかし、我々はそうしたご希望にはそわない。お金が欲しくてプロコーチになりたいのなら、年収で1000万円か1億円ほどの収入を得ることのできる人が、会には何人もいるのである。しかし、そうした人たちも1クラブ員として会費を払って一緒にやっている。
試合場での家族単位の応援や世話やきなどは、せっかく築きあげてきたチームの一体感を損なうものであるが、青卓会の父兄は、“観戦はしても手だし、口出しはしない”といった良い作風を守っている。これもすばらしい情況の一部である。
第4の理由は、社会の情勢である。これがまたすばらしい。たとえば卓球日本の情勢である。
日本の卓球は、中国の文化大革命を契機として崩れてしまった、といえば、いかにも他人のせいにした言いかたでよくない。しかし、中国が出場したとしたら、おそらく女子関係の1~2種目しかとれなかった1967年の世界選手権で、7種目中6種目に優勝したときから狂いがはじまった。
この時ほど“フンドシ”をしめなければならないことはなかった。しかし、実際に勝ちもしないのにカブトの緒をゆるめてしまった。結果は歴然である。
中国が復帰するまでもなく、ヨーロッパにすらやられるようになった。ヨーロッパをいま支えているスウェーデンの選手は、“全盛時代の中国を倒すほど上手な選手”を目標に鍛えられた選手たちである。このハードトレーニングを見ていた他のヨーロッパの選手たちの練習もものすごいもので、67年以来の日本の選手が今のヨーロッパの選手に勝てないのが当たり前である。
しかし、日本はいつまでも弱くあってはならない。
日本の卓球を本当に強くできる指導人は青卓会に多くいる。
これは有利な情況である。
学校の課外活動を基盤にしたスポーツは、第二次大戦後の日本のスポーツを背負ってきた。しかし、経営の弱体化と教師の生活の問題とかか、学校スポーツは一部の企業でしか成り立たなくなっている。しかも、それらの私学でも、企業経営上のメリットがなくなれば、その部は廃止しないわけにはいかない。企業経営のメリットとは生徒増加に結びつくPR効果である。このスポーツはテレビや新聞にどれだけ活字と写真が出るか、ということである。
だから、私企業の学校がスポーツをやるのは、いくつかの伝統ある学校を除けば、“卓球が盛んだからやる”のであって、“卓球を盛んにするためにやる”のではない。これは大部分の企業スポーツにしても同じである。企業スポーツチームの一部の幹部は、“新聞にもっと名前が出さえすれば、もっと会社は金を出す”、とか、“卓球がもっとテレビに出れば、卓球の選手をもっと採用してあげよう”などといっている。
これも前出の私企業経営と同じで、「利益が得られればやるし、得られなければやらない」ということで、スポーツ活動や文化活動ではなく、経済活動そのものなのである。
これは悪い情勢のように見えるが、そうではない。スポーツマンのエネルギーは、こうした経済活動を背景としては出てこないから、青卓会はそれにわずらはされなくてすむからである。
ある大企業の選手たちは、全日本実業団選手権大会で優勝できなかったとき、監督から、“負けるためにお前らを雇ったんではないぞ!”と叱られたそうである。これでは泣いて発奮するどころか、泣いてやめたくなるのが当たり前だ。青卓会にはそうした点がない。一般的な社会情勢は、青卓会のよさをはっきりさせる上で“すばらしい”のである。
青卓会の選手は自力で、進学し、就職し、卓球を続け青卓会を育ててゆかなければならない。これがまたすばらしいことである。このでき上ってしまってシラケている日本の社会の中で、自分たちがつくり上げていく喜びのある組織で、世界に通じているものなど、そうたくさんはない。
スポーツで少し上手になれば、高校に有利な条件で進学することができ、大学に有利な条件で進学でき、大企業に就職できる。これはスポーツ選手が大企業の求める“組織への忠実度が高い”のと、“勉強に時間をあまり使ってないので、危険な思想に毒されていない”などのためである。
しかし実際にこれらのスポーツマンが大企業の中で果たす役割は、組織の方針に従って忠実に動く中堅幹部になることであり、“組織を育てるために変革する力”になることを期待されることは少ない。卓球をやっていた人でも、組織を指揮し、変革もできる力量をもつような新聞社の社長、製鉄会社の副社長などもいる。しかし、これらの人達は自ら勉学し、自ら卓球をやった人たちである。前述したエスカレーター選手(またはところてん選手)ではない。
青卓会の若い会員が勉学とスポーツとの間に板ばさみになりながら自己を鍛えていくことは、“若いうちは買ってでも苦労をしろ”という日本の金言に合致している。最近の週刊誌に出た水泳の某元オリンピック選手のような、甘えっぱなしの発言はおそらく青卓会の選手からは現在も将来も出てこないだろう。
スポーツの訓練は1日8時間ぐらいしかやれないのである。それ以上は体が動かないし、次の日に疲労が持ち越されるからだ。
勉強だって、8時間ぐらいしかできないのである。それ以上は、頭が逆にくたびれて、勉強バカかノイローゼになるのが関の山だ。(勉強に向いている一部の人を除く)。
若いうちは、睡眠は8時間以上は不要である。でんぷんを多く採りすぎたり、就寝前に腹いっぱい食べたりしないかぎり、8時間で充分である。
世界選手権大会会期中での平均睡眠時間は6時間程度である。山中指導委員長が日本チャンピオンとして同時に主将を務め、エースであった66~67年の日本女子チームは、世界女子チーム史上の最強チームであったが、合宿訓練での平均睡眠時間は6時間程度であった。夜中の2時までやっても、翌日の起床はいつもと同じだった。そうした中で選手たちの体重は減るどころが増えさえしたのである。
青卓会にはベンチコーチがほとんどない。これがまた素晴らしいことである。すべてのよいことは、いくぶんかずいぶんむずかしいことである。1+1=2よりもアインシュタインの相対性理論の方が難しいが、数学の問題でなくても難しいものを解決したときの方がよろこびが大きいものである。
指導者に“俺についてこい”としごかれた結果、どれが自分の卓球だかわからないままに数年もやってしまって、しまいにいやになってしまった例は多い。
また、指導者抜きでは何にもできない選手を育てあげ、それをまた喜んでいる指導者もいるのであるが、青卓会の指導者は、こうした弊害を見つくしてきているので、選手の“自力”を育てることを、第一義において試合場での行動を決定しているのである。
“あそこで一言いっていたら勝ったかな?”と思う試合だってある。しかし、その一言を自力で思いつくところにスポーツ活動の成果があるし、そこまで本人がのびるところに指導者の力が発揮されたといえるのである。その一言を自力で思いつけない人は、ほんとうの強豪がずらりと並んだときの世界選手権では、いずれにせよ勝てない。
青卓会で育った選手のうちから世界選手権に挑戦する選手が出るとすれば、その人は、その時の世界のすべての強豪に勝てるように自己を鍛えた選手でなければならない。中国が不在だったら勝てる、とか、スウェーデンがいなければ勝てる、のではいけない。
甘えのない本当に強い立派な選手を育てるには、青卓会のような環境が最適である。
青卓会は挑戦する。
世界は歴史の転換期にある。嵐のまさに来らんとして、風が堂に満つる国際情勢である。
スポーツどころではなく、餓死の恐怖におびえている人達の方がスポーツをやっている人達よりも世界には多いのである。
スポーツをやっている人たちは、こうした情況に同じ人間があることを忘れてはいけない。この人たちは、スポーツよりもパンを求めている。なぜパンが手に入らないのかを考えている。スポーツをやっている国々でも、なぜ自分たちの国は貧しくなければならないのか?と考え続けている人たちも大勢いるのだ。
その中で、甘えた気持ちでオリンピックなどを開くから、“政治に圧倒される”のである。
「人間が2人集まれば政治がある。」というのは政治に関する古典的な説明であるが、古来、政治あっての文化であり、政治ぬきの社会活動など人類は経験したことはない。スポーツをやる人だけが“政治ぬき”などと甘いことをいうから、モントリオールでのIOCのようになるのだ。しからば卓球はどうか。10月のメキシコにはモントリオール以上の国が集まるたった一種目の卓球をやるためにだ。
スポーツが人類のものとして発展していくのであるとすれば、人類の社会の発展にスポーツが合致しなければならない。スポーツ組織とて同じである。IOCは卓球に学ぶべきであるし、特にアジアの卓球界に学ぶべきなのである。
青卓会は幅広い国際活動をくりひろげてきたが、常に視点は上記に合致している。“小さな小さな卓球の球が世界を結び、世界を前進させる”ためにやるのであって、後退させたり、足踏みさせるためにやるのではない。
日本に教わって強くなる国があってもよい。よその国の人だって教える力があるのだから、自分の国の人を強くできない筈はない。よその国の方にすばらしい選手ができれば拍手して讃え、その人を凌駕すべく努力を重ねればよいのである。
青卓会は、まさにそうした意味でも日本卓球界の試金石だ。このままいけば無気力日本卓球界は2部入りは確実。1967年から10年たってみなければ、全体が立ち直るチャンスはない。
卓球日本のブームが少数の人間のケタ外れの努力で生まれ、1960年代半ばまで支えられたことを思えば、青卓会の今の人数さえいれば世界の壁を破ることは困難なことではない。まさに、“世の中に難しいことなどない。敢えて上に登ることを要するのみ”だ。
強くなるとして、その時の作風が青卓会活動の価値を決める。作風を代表するのは選手である。また役員である。関係者である。勝つということはスポーツ活動の結果の1つの面である。目的ではない。とびあがって喜んでみたりもよいけれど、相手の気持ちを察する“情”をもたない態度は犬や猫と同じである。負ける時もそうだ、“鳥の死なんとするや、その声や悲し”というが、自分の都合だけで周囲の人までも巻き込んで悲しがったり嫌な思いをさせたりするような人物には決してなってはいけない。
勝って有頂天になって敗者へのいたわりがなかったり、敗者へのいたわりに作為があったり、相手の気持ちによらなかったりするようであっはいけない。敗れた人への声のかけ方は難しいものである。同様に勝った相手への堂々たる接しかたもまた難しいことである。
青卓会活動は長つづきしなければならない。
継続は力なり、という。
青卓会が本当に天下国家のためになるとしたら、長つづきすればこそ、である。そのためには、社会の発展や変化に応じて会そのものも変わっていくことである。しかし、それは人間の歴史、という長い観点からみたいいかたであって、ここ数年のことをいっているわけではない。
当面の目標は、クラブの自前の練習場を持ち、勉強やその他の支援もできるような経済力を持つことであろう。
本当に卓球が好きでたまらず、青卓会に参加することに生き甲斐を感じる人が、地方や世界の一隅に生じたときに、その人たちを支援できる物質的な基礎を持てるようなになることであろう。この点で若い会員ほど創意工夫が出てくるものであるから、期待したい。
1976年12月
荻村伊智朗